
こんにちは8です。
先日、ちょっと面白い話を聞いたので、その内容+αを綴ってみようと思います。
規制が解除されて、道行く人の賑わいが一気に増しましたね。
そんな中、デパートや電車、または賑わうお店に入ったとき、何だか熱いな、と感じたことはないでしょうか?
家から出たときや、屋外を移動しているときは肌寒く感じても、人込みの中へ入ると場合によっては汗ばむことも。
そんなの人が多いのだから当然では?と、思う方もいるかもしれません。
では、実際にはどのくらい熱さを感じるようになると思いますか?

人が発するエネルギー(熱量)は、性別や年代、また行動内容によって大分変わりますが、およそ100ワットくらいなんだそうです。
ワット・・・と聞くと、まず思い出すのは電球。皆さんのおうちで使っている電球のワット数はいくつでしょうか?
色々あると思いますが、100ワットだとすごく眩しい印象があるため、我が家では滅多に買ったことはないです。
個体差はあるにせよ、人ひとりが、あの熱量を発しているんですね。
ここで皆さん想像してみましょう。
込み合ったデパートの売り場やエレベーター、はたまた閉店間際のお惣菜コーナーetc.
100ワット×その場に居る人数。
そりゃあ、熱くも感じますよねえ。
ちなみに、100ワット相当で動きそうな電気製品って何があるのか調べてみると、デスクトップPCやミキサーなんかが100ワット前後で使えるものもあるみたいです。もちろんピンキリですが。
今まで我慢した分、お出かけに気合いを入れる方もいらっしゃると思います。
人が多い場所へ出かける際は、この話を思い出していただき、暑さ・寒さ対策に組み込んでみるのもいかがでしょうか?
せっかくですので、電球関連のお話をもう少々。

「照明の2020年問題」もあり、急速に普及が進んでいるLEDですが、今まで使っていた白熱電球と何が違うのかと聞かれると、なんだかふわっとしている方もいるのでは?
よくいわれるのが「高価」「熱くない」「省エネ」「長時間使用可能」あたりかな、と思います。
そんなLEDの特徴を調べてみると、大雑把にこんな感じでした。
・寿命が長く、低コスト(白熱電球の約40倍も長く使えるんだとか)
・熱や紫外線をほとんど出さない(紫外線に反応する虫も寄り付きにくくなるそうです)
・低温に強いが、熱や湿気に弱い
・振動や衝撃に強い
・小型・軽量化が可能
・高価
・光の広がり具合が限られている(白熱電球と違って、主に下方にしか広がらないらしいです)
我が家もじわじわとLED電球が増えているのですが、実際に使ってみたときの感想が、「高っ!」「ほんとに熱くない」「なんか暗いんだけど」「前のより長持ちしてる?」だったので納得。
他にも色々ありますが、気になる方は調べてみると面白いかも。
では、実際購入するときの明るさの目安は?となりますよね。
一般的な電球の明るさはワット(W)ですが、LEDはルーメン(lm)という単位を使っているそうです(何故単位が違うのか?まで書くとややこしいので割愛します)。
白熱電球60ワット=全体照明の810ルーメン相当だとか。一部を照らす仕様だともう少し数値が下がるようですが、それにしても全然違いますね。ワット感覚で買うと大変なことになりそうです・・・いえ、なりました。
ちなみに、光の広がり具合に関しては、今現在もさまざまな研究が進んでいるため、以前よりバリエーションが増えたようですね。個人的にはこれが一番嬉しいです。ほんとに暗いんですよ・・・ライトが当たる場所以外・・・。
ということで今回はここまで。
ちょっとしたきっかけで調べ出したとはいえ、LEDについては自分でも全然知らなかったことが多く、参考になりました。これからは失敗しないようにしっかり選んで買おうと思います!
・・・でもやっぱり高い~!
8
広報系の仕事に携わる社会人です。食べることが好きですが、作る方はイマイチ。
------------------------------
中学2年生で習う電力。
「物理」と聞くだけで難しそうと身構える子も多いかもしれません。
電力量・・・ジュール・・ワットアワー・・
・・・覚えることが多くて大変そう!と思う前に、
人ひとりが熱量を発していることを知ることでW(ワット)が身近に感じたり、「そうか、だから人が集まる場所は熱いんだ・・」と妙に納得したり。
生活の中で理科を知り、楽しめるきっかけになるかもしれませんね。
SDGsの授業も学校で行われていますので、熱量の話をご家庭でしてみてはいかがでしょうか~?
この身近に感じる熱量のお話は、小学生のお子さんにも伝えると中学生になった時に「あっ!」と思い出すかもしれませんね!
[ママ広場編集部]

![[1]義母は嫌味の天才です。「いい歳して教育されてないの?」遠回しに私を非難|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami1-2.png)
![[1]子供服マウント?公園で聞こえたおしゃれママの会話が気になる。お下がりクレクレママ|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/mamatomo-osagari1-2.jpg)
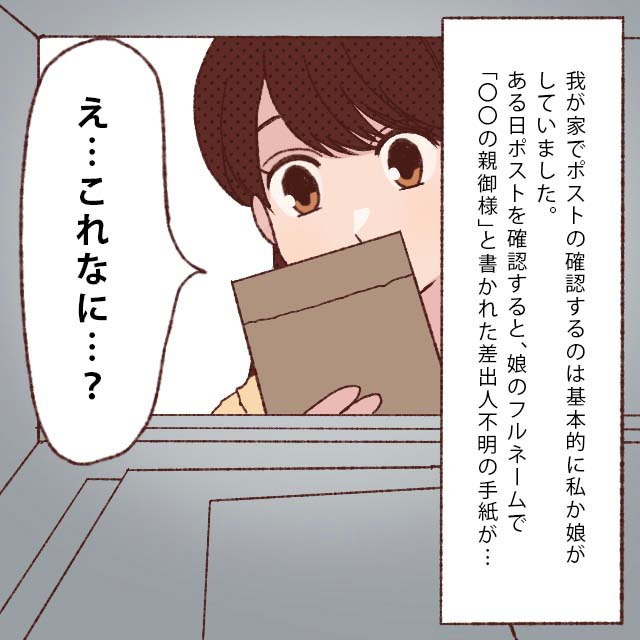
![[1]ママ友チェックは身近なところから攻めてくるー真似ママ被害に遭いましたー|ママ広場オリジナルマンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/manemama-1.jpg)
![[1]白目になるのやめなさい!母だけ恥ずかしい授業参観|小学生男子あるある?ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shougakusei-danshi1-3.jpg)
![[1]マウント女がヤバすぎる!え・・なに?連絡を絶っていた同級生から届いたDM|ママ広場オリジナルマンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/mauntohyouteki-3-1.jpg)
![[1]あの頃は親友だった・・もう会うことのない彼女。友達の彼氏|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/tomodachi-kareshi1-6-640x640.png)





![[1]幼少期に「聞く」力を育てる!には理由があった。「聞く力」ってなに?|ママ広場コラム](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/listening-skills2.jpg)







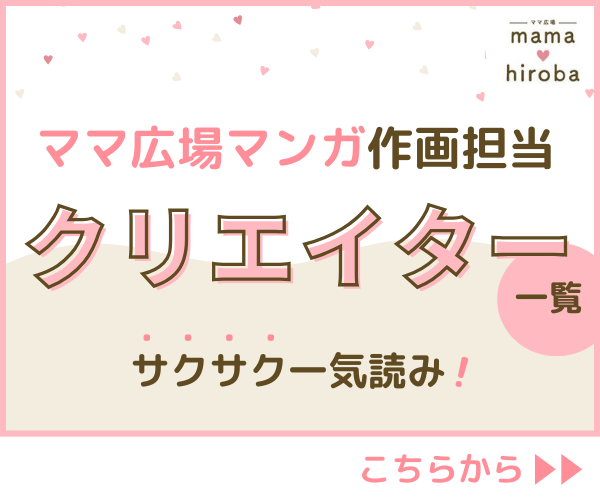
![[1-1]下の子のお食い初めに義母「私がやるって決めてるの!」まだまだ義母に嫌われています|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-1-3-640x640.jpg)
![[1-1]「いいご身分ね」休日昼に突然訪問するなり嫌味な義母。私、やっぱり義母に負けてません|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami-iraira1-3.png)
![[1-1]ゲーム中の背後から感じた妻の睨みに「ちぇっ」渋々息子を公園へ連れて行ったえげつない夫|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-otto-otouto-iya1-3.jpg)
![[1-1]「一列で行くよ~」登校は順調・・ではなかった。うつむく女の子。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble1-3.jpg)
![[1]保育園への送り放棄「遅刻するから行くわ」泣き止まない娘を置いて出勤したうちの夫|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/otto-tomobataraki1-eye-640x640.png)
![[1-1]「もう歩けるの?すごいね!」息子を褒められ「うちの子すごいかも」神童と呼ばれた我が子|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/uchinoko-tensai1-1-1.jpg)
![[1-1]「おまたが気持ち悪い」突然パンツを拒否する3歳娘。触覚過敏「くつ下が履けない」|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shokkakukabin-kutsushita1-2.png)
![[1-1]つい目で追ってしまう・・手を繋ぎ仲良さそうな他人のパパと娘。育児をしない夫|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/otto-ikuji-shinai1-1-640x640.jpg)
![[1-1]え・・イヤ。義母からの電話「次男家族を泊めてあげて」えげつない義弟|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-otto-otouto-muri1-1-1.jpg)
![[1]「俺は見られて困らない」トイレのドア全開の父に中学生娘が大激怒。思春期娘にうざ絡みするパパ|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shishunki-musume-chichioya1-2a.png)
![[1-1]娘誕生で育児に自信満々の夫「できる夫のオレはヘマはしない」起きないオレ、妻の地雷を踏む|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/otto-ikuji-okinai1-2.jpg)
![[1-1]「今から行くわ」こちらの都合を考えない突然訪問。夫の姉がワガママすぎる|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/ottoimouto-wagamama1-1-eye-640x508.png)
![[5完-2]班長がダメなら「学校が責任取って」最善策がわからなかった登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble5-5.jpg)
![[5完-1]また泣き出した娘をスポーツカーでビューン!?女の子ママのワガママに物申した班長ママ。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble5-2.jpg)
![[4-2]先生に言われても付き添いが不満な女の子の母親「一緒に連れて行ってくれないと困る」登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble4-5.jpg)
![[4-1]泣きながら登校した班長「もうやめたい」責任に押しつぶされそう。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble4-3.jpg)
![[3-2]また「みんな先に行って」の事態。女の子を追いかけた班長、旗振り当番ママに助けられる。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble3-3.jpg)
![[3-1]班長に「責任」の重圧。手を繋いで登校するも振り切って逃げた女の子。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble3-2.jpg)
![[2-2]「責任持って連れてって」翌朝も泣き出した女の子を班長に丸投げする母親。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble2-5.jpg)
![[2-1]心では大パニック!全員遅刻を回避し号泣する女の子をなだめる班長。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble2-2.jpg)
![[1-2]どうする班長!?「行きたくない」登校途中で泣き出し動かない1年生の女の子。登校班トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/toukouhan-trouble1-5.jpg)
![[5完]反省しても新たな種が・・トラブル回避は難しい。小学生のお金トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shougakusei-okane5-4.png)
![[4]息子が友達にお金をせびられた?「千円持ってきて」の真相。小学生のお金トラブル|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shougakusei-okane4-3.png)
![お食い初めの大役「養い親」をやりたいと顔にかいてある義母。まだまだ義母に嫌われています[4-1]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-4-1-640x640.jpg)
![みんなに懇願されて大役を引き受けたい義母。催促のチラ見に気づいた嫁。まだまだ義母に嫌われています[4-2]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-4-3-640x640.jpg)
![義母の手腕に一同驚愕で満面の笑み。完璧に整えられた豪華なお食い初め膳。まだまだ義母に嫌われています[3-1]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-3-3-640x640.jpg)
![取り仕切るお食い初めに抜かりなし。衣装まで準備してご機嫌な義母。まだまだ義母に嫌われています[3-2]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-3-4-640x640.jpg)
![融通なんて利かせない!お食い初めの日程を勝手に決定する義母に困惑。まだまだ義母に嫌われています[2-1]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-2-1-640x640.jpg)
![息子のお食い初めを仕切る義母が実家の両親も招待。張り切りすぎる怖さに夫婦で震える。まだまだ義母に嫌われています[2-2]|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-2-4-640x640.jpg)
![[1-2]「断ると後が大変」お願いしたものの義母の張り切りに不安しかない・・まだまだ義母に嫌われています|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-kirawre4-1-5-640x640.jpg)
![[5-1完]真実が明るみに。面倒なことを押し付けられていた私、やっぱり義母に負けてません|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami-iraira5-2.png)
![[5-2完]義母の企て失敗。期待はずれでさんざん嫌味を言われる私、やっぱり義母に負けてません|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami-iraira5-4.png)
![[4-2]毎日しつこい!花の世話を押し付けて画像を要求してくる義母。私、やっぱり義母に負けてません|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami-iraira4-4.png)
![[4-1]ぜったい訳アリ・・問答無用で花の苗を押し付けてきた義母。私、やっぱり義母に負けてません|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/gibo-iyami-iraira4-1.png)


![[8-2]「頑張った娘と私の思い出」ママ友の優しいことばが嬉しくて泣いた・・触覚過敏「くつ下が履けない」|ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shokkakukabin-kutsushita8-6.png)
![[34]氷を噛みしめながら大後悔!出産前は食べるべし!!初めての妊娠・出産inアメリカ|チコの育児漫画](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/kaigai-syussan34-9-640x569.jpg)
![[5・完]私が笑顔になったら娘も笑顔に。リフレーミング実践で起きた変化。見方を変えたら捉え方も変わる|かわいみんの育児漫画](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/kawaimin65-3-640x640.jpeg)
![<息子のためだった>誰よりも息子をわかっていると思っていた。でも無理をさせていたのは母親の私。|神童と呼ばれた我が子[7]ママ広場マンガ](https://mamahiroba.com/wp-content/uploads/shindou-gifuteddo7-3.jpg)
